画像生成AIで作成した画像をブログやSNS、商品デザインなどで活用したいと考えている方にとって、「商用利用できるの?」「著作権は大丈夫?」という不安は大きなものです。本記事では、Canva、Midjourney、Leonardoなど人気の画像生成AIツールにおける商用利用の可否とライセンスの考え方、著作権の基本的な知識について初心者向けにわかりやすく解説します。
商用利用・著作権とは?初心者が押さえておきたい基本
画像生成AIは、今やクリエイティブの常識を覆すほどに浸透し、多くの人が「自分だけの画像をAIで手軽に作れる」時代になりました。しかし、商用利用や著作権という視点になると、話は少し複雑です。
-
商用利用:生成した画像を「広告・販売・収益目的」で使うこと(例:ブログ、YouTube、EC商品など)
-
著作権:画像の「創作した権利」。AIで生成された画像の著作権は誰にあるのか?というのが現在大きな話題です
-
利用規約・ライセンス:各ツールごとに、商用利用や再配布についてのルールが定められています
こうした点を正しく理解することで、トラブルやリスクを避け、安心して生成AIを活用することができます。
✅ Canvaの商用利用ルールと注意点
Canvaは商用利用が可能ですが、次のようなルールがあります:
-
Canvaで生成した画像(Text to Image機能)は基本的に商用利用OK
-
ただし、一部テンプレートや素材、写真のライセンスに注意(Premium素材など)
-
有料素材を使った場合、著作権はその素材提供元にある可能性がある
たとえば、Canvaで作成したサムネイルやバナーをそのまま広告に使用する場合、背景に使われている写真やアイコンが有料ライセンス素材であると、商用利用の制限がかかるケースもあります。そのため、画像を生成したあとで「使用可能か?」を確認する習慣をつけておくことが重要です。
Canva公式ガイド:Canvaのコンテンツライセンス契約
✅ Midjourneyの商用利用は?著作権の扱いは独特
Midjourneyはアーティスティックな画像生成で人気ですが、商用利用については明確な線引きがあります。
-
有料プラン加入者は商用利用可能(画像の著作権が使用者に付与)
-
無料プランでは基本的に「非商用利用」とされ、著作権はMidjourney側に帰属
-
生成された画像の一部は公開ギャラリーに共有される点にも注意
例えば、Midjourneyで生成したイラストを自作グッズに印刷して販売したい場合、有料プランに加入していれば問題ありませんが、無料プランで作成したものを使うとライセンス違反になる恐れがあります。
Midjourney公式規約:Terms of Service
✅ Leonardo.Aiの商用利用とライセンス方針
Leonardo.Aiは、アニメ・ファンタジー系のキャラクター生成で注目されているAIツールです。商用利用については比較的オープンで、以下の点がポイントになります:
-
基本的に商用利用OKと明示されている
-
一部のプリセットやテンプレートには、利用制限が付く可能性あり
-
画像を公開・販売する場合は、生成プロンプトの開示が求められることもある
商用利用できる範囲が広い分、利用規約を読み飛ばしてしまうと、後から「この使い方は違反だった」となることもあります。Leonardo.Aiも定期的に利用規約が更新されるため、こまめなチェックが安心です。
Leonardo公式ライセンスページ:Leonardo.Ai License
✅ ChatGPTで生成した画像の商用利用について
OpenAIが提供するChatGPTやDALL·Eによる画像生成も、商用利用が可能とされています。ただし、以下の点を踏まえて利用しましょう:
-
ChatGPTやDALL·Eで生成した画像は、利用者に著作権が帰属しない(ただし、商用利用のライセンスは付与されている)
-
OpenAIの利用規約に基づき、暴力的・差別的・違法コンテンツへの使用は禁止
-
利用者は、生成された画像の内容に責任を負う必要がある(倫理的・法的配慮を含む)
✅ よくある誤解とリスク
| 誤解 | 実際のリスク |
|---|---|
| 「AIで作った画像だから自由に使える」 | 一部のツールは著作権を主張したり、商用利用を制限している場合あり |
| 「日本語の説明がないから気にしなくてOK」 | 利用規約は英語でも法的拘束力があるので注意 |
| 「商用利用OKと書いてあるから何でも可能」 | 有料素材・第三者コンテンツとの組み合わせには注意が必要 |
AIツールは簡単に使える分、深く調べないまま利用してしまいがちですが、「知らなかった」では済まされないケースもあります。特に、商標や肖像権が絡むような商用案件では、生成画像の使用範囲や著作権の所在に関する証拠が求められる場合もあります。
✅ 安心して使うためのチェックポイント
-
画像生成前に「そのツールの商用利用ポリシー」を確認する
-
CanvaやMidjourneyなどツールごとのライセンスページに目を通す
-
有料素材やテンプレートの使用有無を記録する(エビデンスとして)
-
不安な場合は「自作+CC0(著作権放棄)素材の併用」などを検討
-
生成した画像の使用例や意図をメモしておくと、万一の説明責任に役立つ
関連記事
✅ まとめ|AI画像を安全に使うにはルールの理解が大事
画像生成AIの普及で、誰でも簡単にクリエイティブを楽しめる時代になりました。しかし、商用利用や著作権の問題は「知らなかった」では済まされない重要なテーマです。
本記事を参考に、各ツールのルールをしっかり確認しながら、安全・安心なAI活用をしていきましょう!


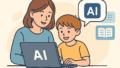
コメント