SNSやプレゼン資料などでよく見かける「いらすとや」のイラストたち。あの独特で親しみやすいスタイルは、今や日本のネット文化の一部と言っても過言ではありません。しかし、近年は生成AIが登場し、「いらすとやのようなイラストもAIで作れるのでは?」という声も増えてきました。
本記事では、「生成AI いらすとや」というキーワードをもとに、生成AIによるフリー素材風イラストの可能性や著作権の注意点、そして“人が描く”イラストの意味について深掘りしていきます。
生成AIと著作権の関係についてはこちらの記事もご覧ください。
「生成AIはイラストレーターの味方かライバルか?」という記事も参考になります。
いらすとやとは?ネットの定番フリー素材サイト
「いらすとや」公式サイトはこちら → https://www.irasutoya.com
「いらすとや」は、かわいくてわかりやすいフリーイラストを提供する人気サイトです。ゆるいタッチで多様なシチュエーションを網羅しており、教育・ビジネス・SNS投稿など幅広い場面で使われています。
特徴:
-
商用利用OK(一部条件あり)
-
テーマの幅が非常に広い(季節・社会・感情・医療など)
-
統一されたタッチで使いやすい
「誰でも使える・どこでも見かける」ことが魅力のいらすとやですが、AIが同様のイラストを生成できるようになると、その存在価値にも影響があるのでは?という議論も出てきています。
生成AIで「いらすとや風」イラストは作れるのか?
結論から言えば、「いらすとや風」のイラストは生成AIでも“それっぽく”作れます。
たとえば:
-
Stable Diffusion + LoRAモデルで、シンプルで平面的なテイストを再現
-
Midjourneyで「ゆるくて可愛いフラットなキャラクター」のプロンプトを入力
-
DALL·Eで「教育向けの柔らかいイラスト」風に調整
しかし本物のいらすとやとは異なり、
-
キャラクターの統一感や背景の整合性が弱い
-
著作権的に“模倣”に当たる可能性がある などの注意点もあります。
まとめ: 技術的には生成可能だが、クオリティ・法律面では人の描いた「いらすとや」にはまだ及ばない部分も。
著作権に注意!「いらすとや風」は危険なグレーゾーン?
「いらすとや風」というプロンプトでAIイラストを作ること自体はできますが、その絵を商用利用・公開する場合は注意が必要です。
-
いらすとやの作風は、絵柄として作者の創作性が強く認められている
-
それを真似した生成AIの作品は「二次創作」または「スタイル模倣」に近い
-
商用で使えば、著作権侵害として訴えられるリスクもゼロではない
ポイント: 「いらすとやに“似たようなもの”をAIで作っただけ」という言い訳は通用しません。安全に使いたいなら、自作プロンプトの調整やオリジナリティの確保が必須です。
AIとフリー素材文化は共存できるのか?
いらすとやのような「親しみのある無料素材」は、インターネット上での表現を豊かにしてきました。そして、生成AIもまた「誰もが手軽に絵を使える世界」を広げる可能性を持っています。
この2つは競合ではなく、役割を分けて共存することが理想です。
-
「短時間で大量に作りたい」→ 生成AI
-
「安心して商用利用したい」→ いらすとや
-
「自分だけの個性を出したい」→ 手描き+AI補助
まとめ: フリー素材文化とAIは対立ではなく“使い分け”がカギ。場面に応じて最適な手段を選ぶことが重要です。
実例紹介:AIで作った「いらすとや風」イラストの現実
例①:教育資料でAI生成の図解を活用
先生が授業資料に使うイラストを生成AIで作成。「いらすとや風」とまではいかないが、場面に合った“かわいくて分かりやすい”タッチに調整。時短効果が大きかった。
例②:ブログのアイキャッチにAIイラストを活用
フリー素材ではなく、自分だけのアイキャッチ画像を作りたいブロガーが、DALL·Eで「やさしい雰囲気のイラスト」を生成。差別化と権利的安心感を両立。
例③:企業のプレゼン資料に生成AIイラスト
社内資料でオリジナル感を出したいときに、Midjourneyで作成した図解風キャラクターを使用。テンプレ感のない資料が好評。
まとめ: あくまで“参考”として使いつつ、商用・公開時は慎重に判断を。
よくある質問(FAQ)|生成AIといらすとや風イラストについて
Q1. いらすとや風のAIイラストをSNSに投稿しても大丈夫ですか?
A. 個人利用であれば問題になることは少ないですが、営利目的や広告で使う場合は注意が必要です。
Q2. いらすとやのスタイルを模倣したAI画像を販売するのは違法?
A. 著作権侵害とみなされる可能性があり、非常にリスクが高い行為です。
Q3. 「いらすとや」とは無関係なフリー素材風イラストをAIで作るのはOK?
A. 問題ありません。プロンプトの工夫で「オリジナル風」に仕上げましょう。
Q4. 教育目的でAI生成イラストを使うことに問題は?
A. 非営利目的で、かつ自作であることが明確であれば、問題になりにくいです。
まとめ:生成AIで「いらすとや風」を扱うなら、個性とルールを大切に
-
「いらすとや風」は再現可能だが、完全な代替にはなりにくい
-
著作権・倫理面では慎重な判断が必要
-
AIはフリー素材文化を広げる可能性を秘めている
-
大切なのは、目的に応じてAIと人のイラストを“うまく使い分ける”こと
生成AIが普及する今だからこそ、いらすとやのような“人の個性がにじむイラスト”の価値も、より際立つ時代になっています。
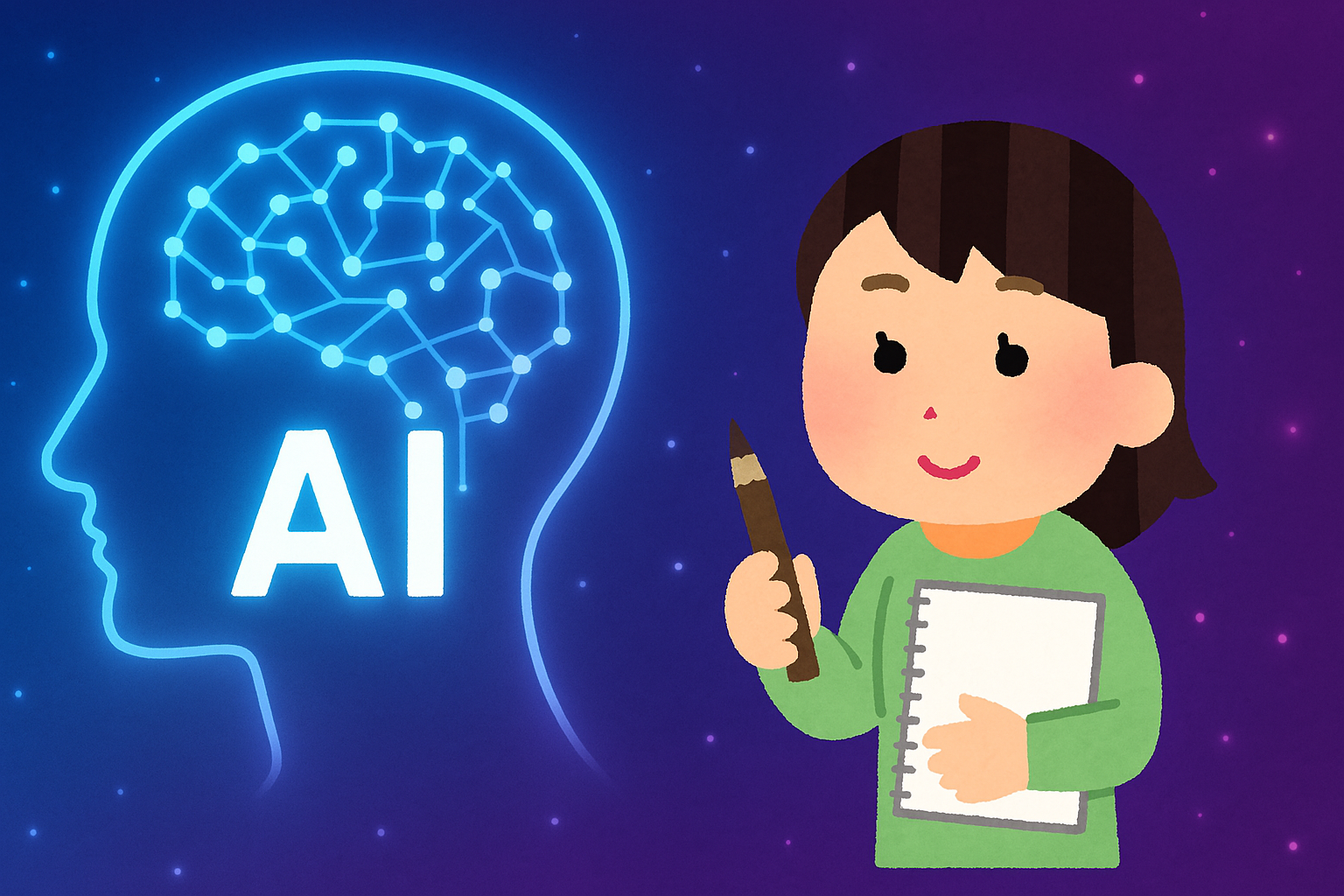


コメント