なぜ「生成AI」と「著作権」が注目されているの?
近年、ChatGPTやDALL·E、Midjourneyなどの生成AIを使って、誰でも簡単に文章や画像、音楽などのコンテンツを作れるようになりました。
しかし、AIが作ったコンテンツをブログやSNSに投稿したり、仕事に使ったりするときに「これは自由に使っていいの?」「誰のものになるの?」といった疑問を感じたことはありませんか?
生成AIによって作られた作品に対して、著作権はどうなるのか? という議論が世界中で注目されています。
この記事では、初心者にもわかりやすく、生成AIと著作権の関係や、知っておくべきポイントを丁寧に解説します。
そもそも著作権って何?
著作権とは、創作した人(著作者)に与えられる、「その作品をどう使うか決めることができる権利」です。
小説やイラスト、音楽、映画など、人が創作したものには自動的に著作権が発生し、無断でコピーしたり、商用利用したりすることはできません。
ポイントは、「人が創作したもの」に権利があるという点です。
AIが作ったコンテンツには著作権があるの?
これは現在も議論中のテーマです。日本では、AIが自動的に生成したコンテンツには、原則として著作権は認められていません。
つまり、AIが一人で作った文章や画像には、法律上の「著作者」がいないという考え方です。
ただし、AIを使う人(利用者)が、具体的な指示や創造的な工夫を加えていた場合には、「人の創作性」があると認められることもあります。
生成AIを使って作ったもの、自由に使ってもいい?
使ってよいかどうかは、次の2つをチェックする必要があります:
-
AIツール側の利用規約
-
商用利用OKか?
-
著作権は誰に帰属するか?
-
クレジット表記は必要か?
-
-
生成に使われた学習データの影響
-
著作物を含む学習データから生まれた作品が、既存の作品に似すぎていないか?
-
たとえば、有名な絵画を模したイラストをAIで作った場合、それが「元の著作物に依拠している」と判断されれば、著作権侵害とされる可能性もあります。
使うときに注意すべきポイント
-
まずはツールの利用規約をしっかり確認することが大前提です。
-
商用利用する場合は特に慎重に判断を。
-
誰かの作品に似すぎたアウトプットは避ける。
-
クレジット表記や利用条件がある場合はきちんと守る。
また、たとえ著作権が発生していないAI画像でも、「他人を誤解させるような使い方」「公序良俗に反する使い方」は避けるのがマナーです。
まとめ 安心して使うために知っておきたいこと
生成AIはとても便利な技術ですが、その活用には著作権などのルールを理解しておくことが欠かせません。たとえば、SNS投稿や資料への挿入、YouTube動画など、生成コンテンツが使われる場面はどんどん広がっています。
特に、作品を発信したり商用で使ったりする場合は、「使っていいかどうか」「どんな条件があるか」を自分でしっかり確認する必要があります。
「知らなかった」ではすまされない場面もあるからこそ、基本的な知識を身につけたうえで、安心して生成AIを活用していきましょう。
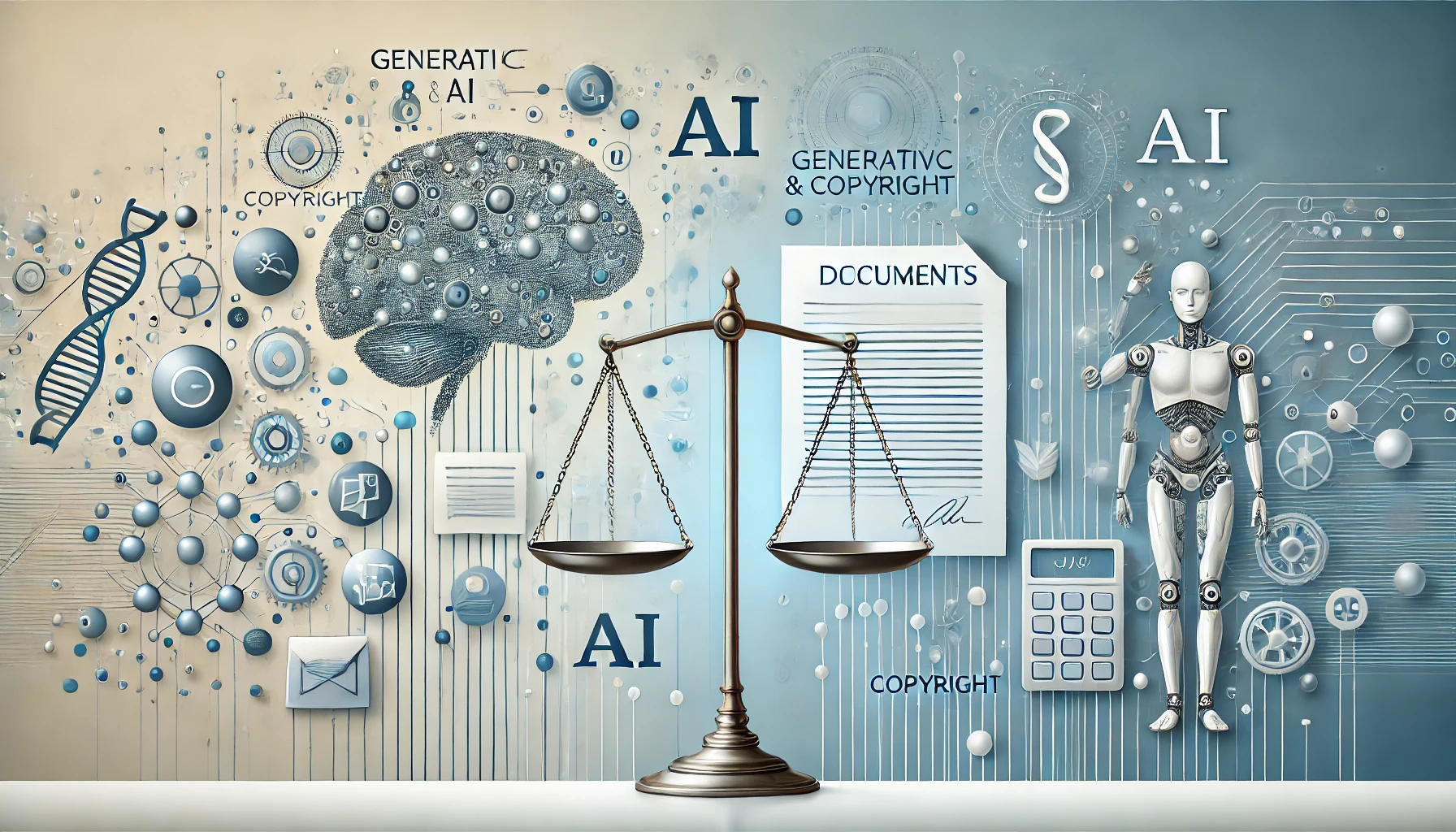


コメント